平熱UPで免疫UP! 強い体を育てる子供服
【平熱UPで免疫UP! 強い体を育てる子供服】
昔は冬でも半袖&半ズボン姿の子供をよく見かけましたが、最近はあまりいませんよね。
寒い冬、子供にどんな服を着せていますか?
大人より平熱が高いといされる子供ですが、最近体温が低い子供が増えています、そこで今回は平熱を上げる着せ方についてご紹介します!
◆冷え症予備軍の子供が増えている◆
手足が冷え眠れない、体がだるい、やる気が出ないなど、体に色々な症状を出す冷え性。
大人だけの疾患と思っていましたが、最近平熱が低い冷え症の子供が増えています。
原因は食生活の変化や、冬でも温かく夏は涼しく過ごせるよう設定された部屋温度、着せているベビー子供服も関係しています。寒い冬、洋服の選び方は赤ちゃんなら大人より一枚多く。
沢山動く子供なら、大人より一枚少なくが基本です。
赤ちゃんならママが脱ぎ着させてあげれますが、自分でお着替えができるようになった子供には、出来るだけ自分で温かい日中は一枚脱ぐ。
寒い朝夕は一枚はおるといった生活習慣を身につけさせたいもの。
画像でご紹介するような、薄手の長そでに半袖を重ね着する子供服は、子供でも簡単に着脱できるのでオススメです。
春先までは上の半袖を脱ぎ着して調節。
暑い日も寒い日も交互する梅雨までは、下に着た長袖を脱いで半袖だけになることも出来るし、夏は半袖だけで着ることもできるので、四季を問わず大活躍しまよ。
◆免疫UPに外気浴&外遊びのススメ◆
年々紫外線が強くなり、日光を浴びることにを危険に感じ、赤ちゃん&子供にUVクリームを使っていませんか?
皮膚がヒリヒリしてしまうほどの日焼けは別ですが、適度に太陽に当たることは子供の成長においてとても大切。
体内でカルシウムを作るために必須となるビタミンDは、太陽に当たることによって作られます。
このビタミンDが不足すると、丈夫な骨や歯が育たないのです。冬の間太陽の光が少なくなるノルウェーでは、乳幼児を健康に育てるために、日光浴をさせる事が、国の条例で義務づけられているのだそう。
赤ちゃんが生まれて1ヶ月過ぎたら、外気浴を楽しんで。肌寒い日は、赤ちゃんに一枚多く着せたり、おくるみで包んでベランダに出るだけでも十分日光の恵みを取り込めます。
日光の危険性ばかり耳に入ってきますが、丈夫な体を作るために必要な太陽の光。上手に付き合い心身ともに丈夫な子供に育ってほしいものです。
◆赤ちゃんを芯から温めるオススメパネルヒーター◆
埃が舞ってしまう不自然なエアコンの風や、ガスファンヒーターを点けた時の空気の薄くなる感じが苦手で、私は冷暖房嫌いだったのですが、とっても寒い朝など、どうしても必要な時があるので、自分にあうそして子供の免疫力に影響を与えない、暖房を探し求めてきました。
オイルヒーターは温かい空気を出し部屋を暖めるのではなく、その空間をじっくり温めてくれるので、質感は気に入っていたのですが、温まるまでに時間がかかり電気代が高くなること。
とても重いので朝は寝室で使い、入浴時は脱衣所に移動して使うなど、臨機応変に移動できない欠点が気にかかるところだったのです。
そんな不満を一掃してくれたのが、画像でご紹介する遠赤外線パネルヒーター。
私は今現在4歳になった3子の新生児時代から使っていますが、部屋を暖める以外にも、ちょっと生乾きの赤ちゃんのお着替えをかわかしたり、赤ちゃんがお風呂から上がって着るものを暖和室の近くで暖めてました。もう新生児はいない我が家ですが、遠赤外線パネルヒーターの前で子供服を乾かすと、赤ちゃんの匂いが室内に充満した幸せな記憶が蘇ってきます。
子供が暖房器具に触ってしまう危険がなくなった今も、お風呂に入る前脱衣所を暖めたり、一人食事の用意をする時に家族のようにやさしく暖めてくれる暖房器具。女性の力でも簡単に移動できるのもGOOD!です。
暖房は必要ですが、寒い冬なのに薄着で居れるほど部屋を温めてしまうと、子供の免疫力は下がります。冬は冬。夏は夏なのです。あまりに快適にしてしまうと子供の体内能力が退化するので、出来るだけ自然に近い形で冷暖房器具は補助的に使う方がいいと思います!


風邪になる原因 メカニズム 肺炎 ウィルスとは?
【どうして季節の変わり目に風邪を引きやすくなるの?】
どうして免疫力が弱くなると風邪を引きやすくなるのでしょうか。
そもそも風邪ってなんですか?
「風邪」は本名「風邪症候群」といい、咳、痰、くしゃみなどの呼吸にまつわる症状と、熱、頭痛などの全身症状、さらに下痢などの消化器症状が出現する病気の総称です。
そして風邪の90%がウイルスによって起こることがわかっています。
言い換えると、風邪とは、主にウイルスが鼻、のど、空気の通り道の上のほう(=上気道)に住みついて(これを感染といいます)、せき、痰、くしゃみなどの症状をひきおこす急性の炎症の総称ということになります。
「かぜをこじらせると肺炎になる」というのは、本来ならのどで治まる炎症がのどから気管、さらには肺(=下気道)といった奥深くまで及んでしまうということなのですね。
◆それではウイルスって何?◆
それではウイルスとはなんでしょうか。
大雑把に言えば「ウイルスは、病気を引き起こす微生物の中で一番小さく、一人ではいきてゆけないもの」と思っていただければよいと思います。
そして、ウイルスには実は抗生物質は効きません。
ですから、基本的には風邪は自分の治癒力=免疫力で治すしかないのですね。
◆インフルエンザは風邪ですか?◆
広い意味ではインフルエンザは「インフルエンザウイルス」というウイルスがひきおこす「風邪症候群」の一種です。
ただ、普通のかぜが鼻やのどやおなかの局所症状が主で、2、3日、長くても1週間くらいで治るのに比べ、インフルエンザウイルスによるかぜは全身症状をひきおこし、しかも症状が重いので、狭い意味では普通のかぜとは区別しているのです。
ですから「風邪」は広い意味ではインフルエンザを含み、狭い意味では含みません。
ちなみに、かつて、世界的に大流行をひきおこした「スペインかぜ」「香港かぜ」などは今の言い方で言えば「スペインインフルエンザ」「香港インフルエンザ」なのですね。
余談になりますが、夏かぜと冬かぜの違いはウイルスの種類の違いといわれています。
一般的に冬のウイルスは低温、低湿度を好み、夏のウイルスは高温多湿を好みます。
ウイルスにもいろいろ好みがあるのです。人間と一緒ですね。
◆どうして風邪は治るの?◆
では、普通の風邪の場合、なぜこじらせなければ炎症はのどまでで治まるのでしょうか?
実は風邪を治すのは、非常によくできた、免疫システムという体の防御反応が働いています。
そもそも、ウイルスに対する体の防御反応と細菌(ばい菌)に対する体の防御反応はちょっとシステムが違います。
細菌は一人で増えることができるので、私たちの細胞の外で勝手に増殖して悪さをします。
ですからお薬(抗生物質)がよく効くのです。
ところが、ウイルスは一人で増えることができないので、まず、私たちの細胞に入り込んで、そこで増えて悪さをします。
いわば、敵が、そうとわからないように味方のなかにはいっているようなものです。
しかし、人間の免疫システムはよくできているので、ウイルスに感染した細胞を殺したり、ウイルス自体も殺すシステムがあるのです。
体からウイルスを排除する期間が5日から1週間、つまり風邪が治るまでの期間はそのくらいということです。
抗生物質はウイルスそのものには全く効かず、風邪ウイルスとの戦いで傷ついた場所に細菌が入って、さらに炎症が広がることを防いだりするために使われます。
そして、風邪薬は、鼻水がひどければ鼻水を止める、咳がつらければ咳を止める役割でしかないのです。
元気なら「風邪薬無しでも風邪が治る」のですね。
◆咳やくしゃみもカラダを守る仕組み!!◆
くしゃみ、鼻水はうっとおしいですよね。でも、これは鼻粘膜にくっついたウイルスを外に流しだす仕組みなのです。
さらに、咳や痰はのどの粘膜についたウイルスを吐き出すためのもの。
そして、発熱は、高熱にしてウイルスを死滅させようというからだの反応の一環です。
「無理に熱を下げないほうがよい」といわれるのも理にかなっているのですね。
ただ、あまりに高温になりすぎると正常な人のたんぱくにも影響があるので、頭を冷やすなどの対処が必要なのです。
たかが風邪、されど風邪。私たちの体の中には様々な仕組みが備わっているのですね。
インフルエンザにはお気を付けください。
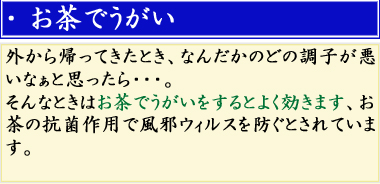
お正月の由来 行事 風習 豆知識
◆門松の飾り方は◆
~門松の由来~
門松は、今では正月の飾りもののように思われていますが、もとはといえば歳神(としがみ)の依代(よりしろ)といわれ、歳神が宿る安息所であり、また、神霊が下界に降りてくるときの目標物と考えられていました。
この歳神とは、別名を「お正月さま」、「若年さま」、「歳徳神」などとも呼ばれ、正月に家々に迎えられる神をいい、昔は白髪の福相の老人だと考えられ、今でも、若者が白髪の老人に扮して、大晦日の夜、家々をまわって子供達を訪れ、お年玉として餅を与える風習の残っている地方もあるということです。
歳神は、年棚(としだな)とか恵方棚(えほうだな)を新しく作って祭るのが普通です。神前には、神酒や鏡餅、白米、かち栗、干柿、昆布、するめ、海老などを供え、歳神に対する感謝の気持ちをあらわします。
~門松の一夜飾りはしない~
門松は、31日にするのを「一夜飾り」といってさける習慣があります。正月は神様をお迎えしますので、一日だけでは、神様を迎える誠意が足りないということなのです。また、29日に立てるのは、「九松」といって「苦待つ」に通ずるということから嫌われています。だいたい12月28日までに立てる家庭が多いようです。
~松の内とは~
松の内とは、元日から、門松を取りはずす日までの期間をいいます。歳神を迎えて、役目のすんだ門松は、普通、七草の7日に取りはずすようですが、地方によっては、4日、6日あるいは15日までと様々なようです。
◆鏡餅の飾り方は◆
~鏡餅の由来~
鏡餅は、「お鏡」、「お供え」、「お重ね」などと呼ばれその由来は、昔、女が鏡の前に飾ったので鏡餅とするもの、あるいは古代の鏡が丸い形をしていたのでその名が残ったとするものなどいろいろです。
ともあれ、これが床飾りとして発達したのは、室町時代以後床の間のある書院造りができてからといわれています。
~鏡餅の飾り方~
地方や家風によって、鏡餅の飾り方は少しずつちがうようですが、次のような形が一般的です。
三方の上に二枚の半紙を四方にたらして敷き、うらじろ(長寿の象徴)とゆずり葉(家系が絶えない象徴)をおき、その上に大小二個の丸餅をのせ、上の餅の頭から昆布を前にさげておき、その上に橙(家が代々繁栄する象徴)をのせます。
伊勢海老が橙をかかえるように水引きで結んでのせたり、ほんだわらを敷いたり、串柿を添えたりしますとさらに豪華になるでしょう。
三方がない場合は、丸盆を利用するのもけっこうですし、飾りかたも、半紙を敷いて、裏白を添え、鏡餅の上に葉のついたみかんをあげただけでも十分です。
~鏡餅の飾り場所~
鏡餅は床の間に飾るのが普通ですが、床の間がなければ、玄関のげた箱の上でも客間の棚の上に置いてもけっこうです。
また、小型の鏡餅にみかんをのせて各部屋ごとに飾ることも行われるようです。
お餅は12月28日までにつく
最近は、自宅でお餅をつくことはめずらしくなりましたが、つく場合は12月28日までにつきます。29日になりますと「九(苦)もち」といって、きらう習慣があるからです。
◆おせち料理◆
~おせち料理の由来~
おせちとはお節句(せっく)からきた言葉です。本来は正月だけでなく、正月七日の人日(じんじつ)、三月三日の上巳(じょうし)、五月五日の端午(たんご)、七月七日の七夕(しちせき)、九月九日の重陽(ちょうよう)の五節句などの式日に用いる料理のことでしたが、今日では正月料理だけが「おせち」よ呼ばれています。
正月におせち料理が普及した理由のひとつには、おせち料理があるあいだは、家庭の主婦も台所仕事から解放されて、休養できるという意味あいがあったといわれています。
~主な料理と詰め方~
おせち料理は地方の風習、家風よりさまざまですが、黒豆は「まめ(健康)」になる、田作は「田を作る」、昆布は「ひろまる」あるいは「よろこぶ」、また昆布は、にんじん、こんにゃくなどを結ぶのは「むつみ合う」、といったように語呂合わせ的な縁起の由来があって、全国的に用意される品のようです。
そして、重箱に入れるのも全国的風習で、重箱は外が黒、中が朱塗りが本式です。重箱におせち料理を詰めるにもしきたりがあり、上から順に一(いち)の重は口取り、二(に)の重が焼きもの、三(さん)の重は煮もの、与(よ)の重が酢のものになります。
また、料理の品数は三、五、七というように奇数にそろえます。
~おせち料理の献立の例~
おせち料理の献立の一例をご紹介しまします。
「一の重(口取り)」
黒豆、数の子、田作、市松かまぼこ、きんとんを色どりよく詰めます。市松かまごこは、紅白のかまぼこを切って組み合わせます。
「二の重(焼きもの)」
ぶりの照り焼き、車えびの艶焼き、いかの松風焼き。ぶりは素焼きにして照りじょうゆで仕上げます。
「三の重(煮もの)」
煮しめの類。棒だら、ごぼう、黒いも、たけのこ、れんこん、高野豆腐、昆布巻き、にんじん、さやえんどう。
「与の重(酢のもの)」
しめぐじの柚子押し、紅白なます、菊花かぶら、しめさごしの八重作り、酢れんこん、はじかみしょうが。なお、ぐじは甘鯛、さごしはさわらの小さいものです。
以上のような料理がおせち料理の基本とされていますが、最近の若い世代の家庭では、このような伝統的なおせち料理でなく、たとえば、ハムやサラダなどを使ったもの、あるいは中華風の正月料理などをそろえて、新年を祝う人もふえてきたようです。
~とり皿を用意する~
おせち料理は最初から小皿に取って出すものではありません。それぞれの重箱に取り箸を用意し、家族も客も、煮しめと酢のものを区別する程度の取り皿を用意して、各自の好みのものを自分で取って食べるようにします。
一つ一つの器に一種類ずつ料理を出していたのでは、せっかく主婦を台所から解放しようとするおせち料理の意味が失われてしまいます。
~三が日分用意する~
今は、正月でも商店は長く休みませんし、同じ料理では飽きてしまいますから、おせち料理は三が日分用意する程度で十分でしょう。昔は正月の七草まではおせち料理だけ食べ、来客に対してもおせちだけでもてなせばよいとされていました。
◆お雑煮◆
~雑煮の由来~
雑煮とは、餅を野菜・魚介類・鶏肉などととも煮る吸物で、正月三が日にこれを食べて新年を祝います。これは、年越しの夜に神を迎えて行った祭りの直会(なおらい)として、神事にたずさわった人々が、神に供えた飲食物を分かち食べた儀式から変化してきたものといわれています。
北九州では、現在でも雑煮または元日の正式の食膳を直会のなまりで「のうらい」「のうし」などとよんでいることがそれを示しています。また、若水や切り火のような神聖な水や火でなかれば雑煮をたかぬというような風習も各地にみられます。
~みそは関西、すましは関東~
関西や四国・九州では、みそ汁仕立てが多く、関東や中部などでは、すまし汁仕立ての雑煮が主流になっています。
これは、江戸時代、武家の多かった江戸では「新年早々、みそをつけたくない」というような縁起をかついで、みそ汁仕立てをきらったのに対し、町人中心の大阪では、「みそ汁仕立てのほうが満腹感がある」というような実利的な考え方から、みそ汁仕立てを主にするようになったのだとする説もあります。
~丸餅と切り餅~
餅についても、関西では丸餅を湯煮して用いるのに対し関東では切り餅を焼いて用います。本来は、丸い餅は円満をあらわすとされています。
~雑煮の具~
雑煮に入れる野菜や鶏肉などの具の種類も、地方や家風によって、さまざまです。
東京付近では鶏やカモの肉、海老、かまぼこなどに青野菜を配し、京都では、サトイモ、エビイモを入れ、焼豆腐やダイコンを配することが多いようです。青野菜の乏しい地方では、ニンジン、ダイコン、こんにゃくなども使われます。また、中国、九州、北陸などではブリ、東北、北海道ではサケを入れたりします。餅のほかに、種々雑多ののものを入れて煮るので、雑煮といわれるゆえんでしょう。
◆七草がゆ◆
七草がゆの由来
1月7日は、七日正月、七日節句とも呼ばれ、朝、七草がゆを作って食べる風習があります。
これは古くから全国的に行われている行事で、大昔は、七草とは米・麦・稗(ひえ)・粟(あわ)など七種の穀物をさし、これでかゆを作って食べてその年の五穀豊穣(ごこくほうじょう)を祈るという農民行事の一つであったといわれます。
これがいつのころからか朝廷の行事にとり入れられ、穀物が、七種の野草や野菜にかわっていったようです。
七草がゆの前日の6日は、野に出て若菜を摘む風習があったことが、宮廷歌人による若菜つみの歌によって、うかがい知ることができます。
この行事は室町時代以後、儀式化し、江戸時代になると武家のあいだでも行われるようになり、正月七日が人日(じんじつ)という五節句の一つに決められました。
このため、このころから広く一般でも行われるようになったわけです。
正月七日に七草がゆを食べると、万病を避けられると言い伝えられています。
◆七草とは◆
昔は米や麦などを七草といっていましたが、今日では、「芹(せり) 薺(なずな) 御形(ごぎょう) はこべら 佛座(ほとけのざ) 菘(すずな) 蘿葡(すずしろ) これぞ七草」と歌に詠まれる七種類の若菜をいいます。
ちなみに、なずなはぺんぺん草、ごぎょうは母子草、すずなはかぶの葉、すずしろは大根の葉のことです。
◆七草がゆの作り方◆
七草がゆの作り方は、米を洗って、米の5倍の量の水を加え強火にかけます。
煮立ったらとろ火にして、ふたをずらしてふきこぼさないようにおかゆを炊き上げ、塩で味つけします。程よく蒸らしたところへ、よく洗ってみじんに刻んだ七草をさっと混ぜ合わせてでき上がりです。
若菜の香りと色が身上ですから、混ぜ合わせたらすぐに召し上がってください。
野菜や果物の不足しがちなこの季節に、不足したビタミンを補い、お正月のご馳走で疲れている胃腸を休めるために、こうしたおかゆを食べるという風習には、古人の知恵がしのばれます。
◆鏡開き◆
~鏡開きとは~
鏡開きとは、正月のあいだ、神棚にそなえ、あるいは床の間などに飾ってあった鏡餅を割って、汁粉や雑煮などにして食べる儀式のことです。
これは、歳神へのお供え物を食べるころによって、一年間一家の無病息災が約束されるという意味があります。
◆鏡開きの由来◆
1月7日を過ぎると鏡餅を下げ、飾りを取り除く家庭が多いようですが、本来は、11日まで飾っておいて、飾りを取り除くと同時に鏡餅を食べるのがしきたりです。もとは正月20日に鏡開きが行われていました。
武家では甲冑(かっちゅう)などの具足(ぐそく)に供えた具足餅をさげてお雑煮にして食べ、この日を「具足開き」として祝ったといい、婦人は鏡台に供えた鏡餅を「初顔」を」祝うといって、ともに20日の行事とされていました。
ところが、徳川三代将軍家光が正月20日に亡くなったため、それ以後は11日に行われるようになったといいます。いまでは、11日に行うのが一般的ですが、地方によっては、4日、6日、7日に行ったり、14日、15日に行うところもなります。
◆鏡餅は刃物を使わず割る◆
鏡開きの名称は、「切る」ということを嫌い、「開く」とめでたくいったことに由来します。
したがって、鏡開きの餅を包丁などで切るのは禁物で、手またはつちでたたいて割ります。
しかし、最近では暖房のきいた部屋に置いてあったお餅には、かびもたくさん生えていることでしょうから、この際、かびは削る取ってしまったほうがいいでしょう。
また、汁粉にしたのでは歯がたたないかたい鏡餅も、小さく割って油で揚げたり、いったり、また、なめられる程度のからさの塩水に2~3日つけておき、水を切ってから電子レンジで1分~2分加熱するとおいしくいただけます。
【詳しくは】
http://www.yuzawa-gh.co.jp/annualfunction/syougatu/syougatu_main_frame/syougatu_main_frame.htm

年末の大掃除 効率の良い手順
◆大掃除の「効率よい手順」◆
「家中まとめて上から下の順にきれいに」していくことです。 まずは天井から始めます。 天井は意外にほこりっぽいので、ほうきなどに古いストッキングを巻き付けて 静電気でホコリをキャッチ!(照明に当てて割らないように・・・) 次は照明器具。外せる照明カバーは外して、ベランダやお風呂場で洗います。カバーに傷がつきそうなら、バスマットを敷いて掃除するとよいでしょう。 タバコのヤニや油汚れは、弱アルカリ性の住居用洗剤とクリームクレンザーを混ぜると効果的。平面はスポンジで、凹凸のある場所は古歯ブラシを利用します。 天井が終わったら、今度はカーテンレールや窓ガラス、そしてキッチンなどの水周りに走りましょう。特にキッチンのレンジフードのシロッコや五徳などの汚れがひどい場合は、40~45度くらいのお湯を張ったバケツや衣装ケースに、「漬け置き」しておき、汚れを緩めている間に、他の場所を掃除しましょう。 漬け置きの間に、トイレや洗面化粧台、スイッチプレートの掃除などなど。 最後の最後に「床面の掃除機、拭き掃除」、というのがスマートな手順です。 ただ、1日でこれを一人でこなすのは、プロのお掃除やさんでもほぼ不可能なこと・・・。 大掃除に疲れて、お正月に疲れて寝込んでしまった……ということのないように、「7日間計画」などのプランを立てて、無理なく進むようにしましょう。 お料理と同じく、お掃除というものも「手順と計画」が大切ですね。 よいお正月を迎えることができるよう、皆さんも頑張ってください(^^) 【お掃除に関するHP】 http://www.kis.gr.jp/page/kis-lec.html http://www.duskin.jp/jiten/ http://www.duskin.jp/oosouji/dandori/index.html http://allabout.co.jp/family/simplelife/closeup/CU20041225A/index.htm?FM=rankd http://allabout.co.jp/1/222289/1/product/222289.htm http://allabout.co.jp/contents/sp_housecleaning_c/59/19849/index/ http://allabout.co.jp/contents/sp_housecleaning_c/ecokaji/CU20091119A/index/ |

週間CD・DVDランキング
≪CD≫
1位『スワンソング(完全初回限定盤)』 KinKi Kids
2位『いままでのA面、B面ですと!?(通常盤)』 GReeeeN
3位『愛すべき未来へ(初回生産限定)』 EXILE
4位『EXILE LIVE TOUR 2009 “THE MONSTER』EXILE
5位『気まぐれプリンス』モーニング娘
6位『ayaka’s History 2006-2009』絢香
7位『Loveless(初回盤B)』山下智久
8位『スワンソング』KinKi Kids
9位『哀しみはきっと(初回生産限定盤) 』UVERworld
10位『君にサヨナラを(初回生産限定盤)』桑田圭祐
≪DVD≫
1位『ごくせん THE MOVIE』 仲間由紀恵
2位『天使と悪魔 コレクターズ・エディション』 トム・ハンクス
3位『ハリー・ポッターと謎のプリンス 特別版』 ダニエル・ラドクリフ
4位『EXILE LIVE TOUR 2009 “THE MONSTER”』EXILE 』
5位『HISTORY in JAPAN Vol.4 』東方神起
6位『PLAYZONE2009 太陽からの手紙』Kis-My-Ft2
7位『銀魂 シーズン其ノ四 1(完全生産限定版)』アニメーション
8位『“ロイヤル ストレート フラッシュ” LIVE IN YOYOGI DAIICHI TAIIKUKAN 2009
』ポルノグラフィティ
9位『機動戦士ガンダム00 スペシャルエディションI ソレスタルビーイング』アニメーション
10位『涼宮ハルヒの憂鬱 5.285714(第3巻) 限定版』アニメーション
(e-hon 調べ)






